
私達、国際協力NGO「HOPE~ハロハロオアシス」は、フィリピン・セブ島に現地事務所を設けているNGOです。
フィリピンは、美しい海を満喫できるビーチリゾート地として有名です。また、都市部には昼夜楽しめる歓楽街や大きなショッピングモールもあります。
しかし、その半面、貧富の差は激しく、都市部に隣接する地域にもスラムは広がり、困難な生活を強いられている人々がたくさんいます。
そこには、環境、教育、医療、薬物、犯罪、児童労働・売春、ストリートチルドレン、人身売買、宗教、、、様々な問題が渦巻いています。
私達は、現地のスラム(貧困地域)の真ん中に事務所を設け、「スラムの子どもの施設」「スラムの子ども図書館」の運営、チャイルドサポーター(スカラシップ)、フェアトレード、医療支援、生活・学習支援、環境整備等の活動を行っています。
現地にその軸足を置き、現地の人々と協力し、スラムの人々の自立につながる本当の支援とは何か、と常に試行錯誤しながら、草の根の活動を続けています。

そんなフィリピンの南部に位置するミンダナオ島マラウィ市で、2017年5月にイスラム過激派組織と政府軍の間で大規模な戦闘が発生し、現在もまだ戒厳令が発せられています。その内戦により、死者は1200人以上、そして、40万人以上が避難生活を余儀なくされたことは、日本ではほとんど知られていません。
NGOでは、未だ内戦状態が続き、戒厳令下のフィリピン・ミンダナオ島のマラウィ市付近の避難所・キャンプにて、内戦による避難民への救援活動を行っています。
主な活動は、避難所における、食料や衣服、生活支援等の物資の配給、炊き出し、医療支援プロジェクト等です。
ただ、こちらの活動に際し、現在、NGOとしての予算を用意することが困難で、スタッフの私費の持ち出しでの活動となっている状態です。
ふだんの支援地域であるフィリピン・セブ島のスラムの活動においてさえ、資金が足りない状態ですので、それは初めからわかっていたことですし、仕方ないのですが、もしお願いできるのでしたら、皆様にのご援助を頂きたいと思い、ご協力をお願いさせて頂きたいのです。
たとえ現状は内戦で壊滅的な状態だとしても、いつかまた故郷に帰れる日のために、何とか今、この生活を支え、生きのびていかなければなりません。
そこには、この避難民キャンプで生まれた新しい生命もあります。この子たちの未来のためにも、明日への希望のためにも、今、この状況に負けてはいけないのです。
もしかしたら、ただの遠い海の向こうの出来事なのかもしれません。
それでも、もしもこの活動にご理解頂けましたら、ご支援をお願い致します。


内戦の地であるミンダナオ島・マラウィでは、もう数十年に渡り、内戦が続いています。圧倒的なキリスト教国であるフィリピンにおいて、少数派のイスラム教徒が暮らすこの地域では、やはり様々な問題が生じました。ムスリムに対する差別や偏見(日本人の感覚ではむしろピンとくるのではないでしょうか)もありました。ただ、それでもそれぞれの慣習を守りつつ、不満もいろいろくすぶりながらも、それぞれが生活の中で融合し、多くの民衆は平穏に暮らしていました。しかし、一部の過激な不満分子が、反乱・戦闘行為や誘拐等を行い、世界的にはまったくといっていいほど話題にならないくらいではありますが、小規模な混乱は続いていました。
その流れが劇的に変化したのは、近年のIS(イスラム国)を初めとする、中東におけるイスラム過激派の台頭です。I S、マウテグループやアブサヤフといった過激派組織に忠誠を誓う組織がマラウィ市を占拠し、政府軍との大規模な戦闘へと突入したのは2017年5月23日のことです。ドゥテルテ大統領はすぐさま戒厳令を敷き、現在へと続いています。そして、中東において討伐された残党や武器がアジア、ここに流れ込み、逆に、この地域のイスラム過激派の勢力が増したのです。
それは大規模な戦闘に広がり、多くの住民が被害を受けました。
NGOではこの内戦の勃発から準備を重ね、昨年2018年末、現地へ赴き、多くの避難民が生活している戦闘地帯近隣のイリガン市の避難所・避難民キャンプにて、食料配給等の、救援活動を行いました。


内戦により家を壊された人々は、周辺の地域、多くはマラウィのすぐ隣のイリガンに避難し、政府やNGOの支援もあり、多くの避難所が設置され、そこでの生活を余儀なくされました。
また、それが本当に深刻な問題を背負い、複雑な思いにさせられるのは、
その背景が何であれ、こうして多くの避難民を生む直接の原因は、イスラム過激派が起こした戦争で、しかしそれはイスラム教徒の居住区で行われ、被害を受け、家を破壊され、多くの死傷者がでて、避難所生活に苦しんでいるのも、また同じイスラム教徒だということ。
戦闘の激化により戒厳令が発せられ、故郷を追われて、被災者たちの、各地の避難所での生活は、もう2年以上が過ぎました。
NGOでは、そのようなイリガンの避難所において食料配給等の救援活動を行いました。
しかし、ここは、先ほど触れたような、政府が設置した避難所ではなく、避難民による自主的な避難所であり、よってほとんど支援が受けられていません。
住民によると、内戦から避難してきた当初は、現地のNGOによる支援が少しあったようですが、それもすぐに止まってしまい、もうずっと長い間、何の援助もない、ということです。
もともと差別的扱いを受けていたイスラム教徒が、家も仕事も失い、他の場所に避難し、支援も受けてもいない、、、
それが今回、NGOが救済活動をした人々でした。
ここは、そんな「忘れられた避難民キャンプ」でした。

私達のNGOは、ふだんは同じフィリピンではありますが、セブ島で活動しています。
しかし、このミンダナオ島での内戦の話を耳にし、被害を受けた人々を救うために何かできないだろうかと思いました。そして、その支援の話を、いつも一緒に活動しているスタッフや、提携団体のリーダーとかにしました。すると、、、みんな、「バカげてる」「死にたいの?」「誘拐されるよ」という反応で、協力どころの話じゃありませんでした。
でも、思いました。
よく言われている「今、できることを精一杯」「自分にいったい何ができるのか」、、、
本当に困っている人たちのために、自分が今、できること、、、
それがもし内戦状態の中東のシリアとかでしたら、戦場カメラマンでもジャーナリストでもなく、また、何のツテもない、結局ただの一般人の自分には何も手を出せません。本当に死ににいくようなものです。
しかし、同じ内戦でも、ここはフィリピンです。
長年、関わってきて、ある程度勝手もわかってますし、知り合いもたくさんいます。
だから、
自分にも何かができる。
何か、「今できる精一杯」をしなければならない、、、
そして、動き出しました。
たくさんの知り合いに声をかけ、つながり、興味を持ってくれた人と話し合い、やっと数人の協力者が生まれました。
困難な状況にある人々の救いの声に応えるために、
少しずつ、手探りで、それでもなんとか前へ進んでいきました。
何かが起きることも覚悟はしてました。不安もたくさんありました。
でも、なんとかなるんじゃないか、と、自分の覚悟と使命を信じて、勇気を奮い立たせながら、
一歩一歩、きっと明日への希望へと繋がる、今は何も見えてこないけど、でも、そんな未来への道を作っていきました、、、

内戦地域での活動といっても、別にあえて危険なことをする必要はないですし、死にに行くつもりもありません。
ですので、情報や人との繋がりを辿り、少しずつ準備をし、現地入りしました。
とはいえ、招待や案内をしてくれる団体や人がいるわけではなく、とにかくまずは様子を見に、現地へ行ってみよう、というところからです。
そして、、、
いざ、マラウィの隣のイリガンに宿をとり、活動をしようと動き出すと、頼りにしようとしていた現地のNGOとの連絡は途絶えてしまい、直接、事務所を訪ねてみても、扉は閉ざされ、人気がありません。
途方に暮れてながらも、とにかくやるだけのことはやってみよう、と思いました。
町のいろんな人に聞きながら、いくつかある避難所の情報を手に入れ、ジプニー(軽トラの荷台を改造したフィリピンローカルな乗合バス)を乗り継ぎ、たぶんこの辺だろうという辺りまできて降りて、また付近の人に尋ね、そしてなんとかたどり着きました。
廃校の朽ちかけたバスケットコートの脇に、ブルーシートで補強されたテントが並び、人々が生活していました。
それが、今回訪れた、政府の支援の手が届いていない避難所です。
それは、本当に、忘れられたように、町外れの山の中にありました、、、
遊んでいる子どもたちが、おそらく珍しいのでしょう、恥ずかしがりながらもこっちをすごく見て、気にしています。
手をふると笑顔でふりかえしてくれるヒジャブの少女たち。
でも、近付こうとすると恥ずかしがって逃げてしまいます。
でも、ずっと付いてきます。
振り向くとまた逃げてしまいます、、、
そして、テントに行ってみました。
そこにはひとりのおばあちゃんがいました。
たくさんの話をしてくれてました。
今までのこと、現状、不満、不安、そしてあの日のこと、、、たくさんのことを、、、


「もう、一年も何も支援をされていないわ」
おばあちゃんが訴えます。
戦争で家も仕事も何もかも奪われ、仮設テントでの生活。
「支援がないと生きていけない。
でもなんとかみんなで協力してがんばってる。
これからのことを考えると不安で仕方ない。
でも故郷へは帰れない。
帰っても、そこにあるのは破壊された瓦礫の山だけだ、、、」
いろんな話をしました。
そして、ここでの救援活動のことを相談しました。
今、何が必要ですか?
仮設住宅が立ち並ぶ村を訪れ、集まってくれた人たちと話し合いました。
食料と、あと、石鹸とかの生活用品、、、やはり今足りないのは、生きていく術の基本的なものです。
翌日からの救援活動の段取りを決めて、村のリーダーにも話を通してもらって、遠巻きにずっとこっちを気にしてる子どもたちに愛想を振りまいて、
そんなふうに、この地での、私達の救援活動は始まりました。


昨年末からの救援活動を始め、今年の3月には、日本からボランティアのドクターの協力で、鍼灸の医療支援プロジェクトを行いました。
また、イリガンに避難している方の故郷(内戦の地)であるマラウィ郊外に大きなキャンプ(避難所)があり、戒厳令下の地域のため、外国人はなかなか入れないのですが、避難民同士の繋がりで、その避難民キャンプへの支援を行うことになりました。
私たちは、内戦によりすべてを破壊され、避難してきた方々が、いつか無事に。安心して故郷に帰れる日のために、避難民キャンプの現在の厳しい生活を支え、そこに暮らす人々と協力しあいながら、活動を続けていこうと思っています。
しかし、しょうじきな話、資金がありません。
自分は、この救援活動を行うNGOの代表を務めていますが、NGOの活動でお金を得ているわけではなく、普段は他の仕事をしています。過去2回の現地入りについて、主な資金は、自分個人が日本で働いたお金の持ち出しで行いました。
そんな状態の中、被災地の継続的な支援のための資金を、今回お願いしようと思い、クラウドファンディングに挑戦しようと思いました。
主に希望しております支援として、救援物資の購入や輸送にかかる費用への支援をお願いします。
活動については、投稿者が代表を務めておりますNGO「HOPE~ハロハロオアシス」が主催となり、本文でふれております、マラウィ郊外とイリガン市内の避難民キャンプ・避難所へ、直接の支援を行います。
また、すべてのスタッフはボランティアで行い、人件費はかかりませんが、セブ島の現地事務所からの飛行機での移動や宿泊費などもかかってしまい、その費用へのいくらかの補助についても、今回、お願いしたいと思っています。
主な資金の使い道は、
《Ⅰ》活動費用として1100000円
次回以降の予定されている、2019年12月、2020年5月、の2度の活動について、下記①~⑤を2回分の活動費用です。
(もちろん状況によりその後も救援活動は継続しますが、現在、具体的に計画されている2回についてです。)
①マラウィ郊外と、イリガンの難民キャンプの、避難民、約250世帯への救援物資(食料、生活物資、医薬品等)の配給 → 250000円(一世帯1000円分程度)
②寄付して頂いた救援物資(古着等)の輸送費用 → 50000円
③避難所の家屋やテントの修繕費用 → 150000円
④スタッフ(5人)の一週間分の宿泊費、食費への補助 → 50000円
⑤現地移動費(空港~被災地、市街移動費、イリガン~マラウィ移動費)、セブ~ミンダナオ間の航空運賃(同5人分往復)への補助 → 50000円
《Ⅱ》また、当クラウンドファンディング掲載における手数料14%(目標支援金を達成の場合)とリターンの費用を見積り、 250000円。
そうして《Ⅰ》《Ⅱ》の合計が、1350000円となります。
皆さまのあたたかいお気持ちと、ご支援を、お待ちしています。



以下のようなリターンをご用意させて頂きました。
いずれも、現地の方々や子どもたちからの、心のこもった贈り物です。
皆さまからのあたたかいご支援・ご協力、お待ちしています。
①支援する子どもたちからの写真付きサンクスカード
②NGOのニュースレター
③現地の子どもたちの写真のオリジナルポストカードセット
④NGOが支援する地域のお母さんたちの手作りのフェアトレード製品(貝細工アクセサリー)
⑤NGOが支援する地域のお母さんたちの手作りのフェアトレード製品(フィリピンのジュースパックによるリサイクルポーチ)
⑥NGOの活動と、現地の子どもたちの笑顔がいっぱいのフォトブック
⑦NGOのオリジナルTシャツ(色は赤、XS,S,M,L,XLよりサイズを選択できます。)
⑧HP、facebookページでのお名前の掲載、また、NGOの運営するスラムの子どもの施設において名簿パネルへの掲載
⑨10年間、NGOの本会員への登録
※詳細はリターン欄にて。


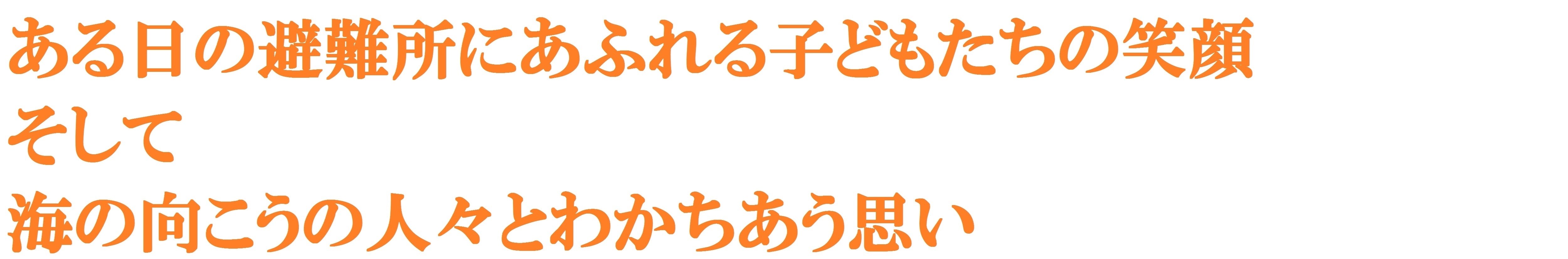
地元の市場で救援物資のお米や缶詰、生活物資、避難所の子どもたちへのプレゼントのお菓子をたくさん仕入れました。
手配したジプニーに荷物を積んで、村に行き、そして、避難所の人たちと一緒に、物資のパッキングをしました。
いつのまにかたくさん集まった避難民の方たちを、なんとか整理して、救援物資を配りました。
みんなとても嬉しそうでした。
配給に一段落がついたあと、集まってる子どもたちとゲーム大会をしました。
そういえば、何気に「みんなでおっきな輪を作ってー」って言ったら、見事に男女別のふたつの輪ができました。
イスラム教の子どもたちは、やはり男女間の接触に厳しいということなのでしょう。
クリスマスソングでも歌う?と言ったら、キョトンとされました。
文化の違い、宗教の違い、それはもうどうしようもなく根付いています。
でも、そんなの、こうやって人と人とがあたたかくふれあっている中では、本当はべつにたいしたことじゃない。「あ。そっか。そうだよね。気づかなくてごめん。」で済むようなことなのです。
なのにそれが、差別や誤解を生み、憎しみの連鎖となり、戦争へと繋がり、こうしてたくさんの被災者が生まれてしまうのです、、、
「でも、今はいい。忘れよう。
この楽しい時を、もう少しだけ、みんなで分かち合おう、、、」
ゲームの賞品は抱えきれないほどのお菓子がいっぱい。
気がついてみると大人も一緒に混ざってます。
勝手に体が動いて、わきあいあいあと、みんなとても楽しそうでした。
きらきらした笑顔がたくさんありました、、、
そして、
いつのまにか一日が終わり、自分らも帰る時間になりました。
最後にみんなで歌を歌いました。
持っていったギターを弾いて、輪になって歌いました。
「キミはひとりじゃない。
こうして一緒に笑顔を分かち合える、、、」
そんな思いをこめて、、、
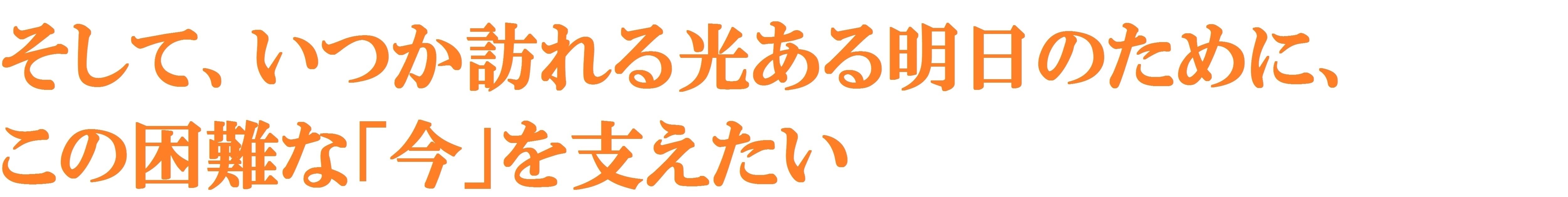
今回の活動に際し、たくさんの方に支援・手助けをして頂きました。
「自分は行けないから」と、支援金を援助してくれた方たち、
アドバイスや情報をくれたフォトジャーナリストの方、
ボランティアで医療支援をしてくれている日本のドクター、
周りがみんな反対ばかりなのに、どんな危険がまってるかわからない戦地へついてきてくれた現地アシスタントの3人、
やばいくらい無愛想だけど、なんだかんだと協力してくれたゲストハウスのおばちゃん、
いろいろ教えてくれたり案内してくれた町の人たち、
避難所で生活する、困難な境遇の中でも、なんとか強く行きていこうとしている人たち、
そして、、、
ここにもある、たくさんの笑顔、、純粋な瞳の子どもたち、、、
「みんな、ほんとにありがとう、、」
帰り際に、仮設テントで暮らす少女が、
「もう帰っちゃうの?」
「きっとまた来てね」
と、抱きついて離れませんでした。
この子の弟は、まだ赤ちゃんで、このテントで産まれたのです。
初めはあんなに恥ずかしがってた子どもたちも、
いつのまにか写真を撮る時に、ヒジャブで隠してた顔を見せてくれました。
「うん、、
また来よう。
いや、来なきゃいけない。
誰に理解されなくてもかまわない。」
もしかしたら危険が待ってることもわかってます。
まじめな話、資金もありません。
でも、ここに、救いを求めてる人たちがいるのです。
待っててくれる人たちがいます。
「だから、
きっと、また来るよ、、、」
きっと、、、
忘れられた避難所の、粗末なテントで、困難な生活を強いられている人々が、それでもせいいっぱい生きています。
いつか、故郷に帰れる日が来るのを夢見て、、、
そのために、生きて明日を迎えるために、またもと通りの安心した生活が待つ未来のために、今、この時の生活を、支えたいのです。
皆様のあたたかいお気持ちと、ご支援を、心よりお待ちしています。







 長い文を読んで頂きありがとうございました。
長い文を読んで頂きありがとうございました。
国際協力NGO「HOPE~ハロハロオアシス」代表・松沼裕二
最新の活動報告
もっと見る
もうすぐ現地入りです。
2019/11/28 08:59皆様、ご支援・ご協力、ありがとうございます。NGO「HOPE~ハロハロオアシス」の松沼です。12月4日より、自分と数人のスタッフが、また現地入りし、支援活動を行います。今回は、内戦地域の視察と、避難民キャンプにおける個別ケア、支援物資の配給、子どもたちへのチャリティーイベントが主な活動になります。このクラウドファンディングはあと数日で終了します。このままでは、おそらく目標金額には達しないとは思います。しかし、それでも、待っている人たちがいる限り、私たちは現地へ向かいます。もちろん限界はありますが、今、できる限りの支援を、気持ちを届けてきます。困難な状況に苦しむ人々のために、そして、子どもたちの未来を、笑顔を守っていくために。応援して頂いた皆様、本当にありがとうございました。そして、あと残り数日ですが、最後までよろしくお願い致します。 もっと見る
草の根の支援
2019/11/25 12:06皆様、ご支援・ご協力、ありがとうございます。NGO「HOPE~ハロハロオアシス」の松沼裕二です。内戦からの避難から時が経ち、人々の中には、テント生活から、地域の避難民キャンプに手作りの家を建て、住んでる方々もいらっしゃいます、私たちの活動にも協力して頂いている村のご理解により、切り開いた山に小さな家が作られ、点在しています。NGOでは、そのひとつひとつの家を訪問し、「今、何が必要か」「何が困っているか」「生活の状態はどうか」等を話し合い、それぞれのニーズに合った草の根の支援をしています。いつか故郷に帰る日が来るのか、それともこのままずっとここで暮らしていかなければならないのか、まだ先は見えていません。それでも、きっといつかやってくる安心した未来の生活のために、「今」をなんとか生きていかなければなりません。私たちは、未来へと繋がる、その「今」を支援しています。皆様、もしよろしければ、私たちに力を貸して下さい。そして、内戦の被災者の皆に勇気を希望を与えて下さい。皆様のあたたかいご支援・ご協力、お待ちしています。 もっと見る避難民キャンプの前で、、
2019/11/20 16:23皆さま、ご支援・ご協力、ありがとうございます。NGO「HOPE~ハロハロオアシス」の松沼裕二です。被災者の子どもたちとスタッフや医療支援プロジェクトのボランティアドクターみんなで遊んで、写真を撮りました。後ろにあるのは避難所の仮設住宅です。といっても政府や自治体が建てたものではなく、自らが、ベニヤとトタンとビニールシートで作った粗末な建物です。それでも今は大切な我が家です。この不自由な生活がいつまで続くのかわかりません。いつか故郷に帰れる日まで、なんとかここで、負けないでがんばっていくために、自分たちもできる限りの支援をしています。もしよろしければ、ご協力頂けたら嬉しいです。困難な生活の中でも笑顔でいてくれる、この子たちのためにも、一緒に希望や力、思いを分かち合いましょう。皆さまのあたたかいご支援・ご協力、お待ちしています。 もっと見る




















コメント
もっと見る